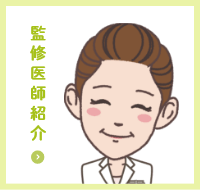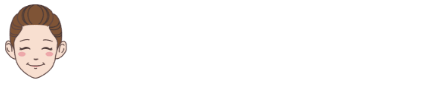甲状腺の病気と妊娠・出産
病気の影響はあるが、治療をしていればだいじょうぶ
甲状腺ホルモンが多すぎたり少なすぎたりする甲状腺機能異常になると、流産や早産、妊娠高血圧症候群などのリスクが高くなります。また、胎児にも影響が出る可能性があります。
ただし、それは病気(バセドウ病や橋本病)になっていることに気づかず、治療を受けていない人の場合です。
「甲状腺の病気になると子どもができない」といった誤解をする人がいますが、それはまちがいです。
こういった誤解をしないためにも、きちんとした治療を受けることが大切です。適切な治療によって、妊娠中に甲状腺ホルモンの状態が正常に保たれていれば、流産や早産を防ぐことができ、健康な人と変わりなく無事に赤ちゃんを産むことができます。
甲状腺機能低下症を治療しないと、不妊の原因になることも
橋本病(甲状腺機能低下)では、排卵がなくなったり、高プロラクチン血症(下垂体から分泌されるプロラクチンには月経や排卵を抑える働きがあり、これが多くなる)をまねくことがあり、不妊の原因になります。また、甲状腺機能低下が妊娠にあたえる影響としては、流産、早産、妊娠高血圧などのリスクが増大します。
ただし、これも治療を受けていない場合です。
潜在性甲状腺機能低下症であっても、妊娠を希望するなら、胎児のためにも治療する必要があります。
甲状腺ホルモン剤で足りないホルモンを補充する治療をすれば、妊娠は可能ですし、胎児にも影響はありません。
甲状腺ホルモン薬は、適量を服用している限り、薬の副作用は特にありませんし、妊娠中や授乳中でも安心して飲めます。
なお、妊娠中は、甲状腺ホルモンの必要量が増えます。橋本病の人は、血液中のホルモン濃度をチェックして、薬の補充量を30~50%増量し、調節する必要があります。
そして、分娩が終われば、妊娠前の補充量に戻します。L-サイロキシンは、わずかに母乳中に分泌されますが、完全授乳にはまったく支障はありません。
バセドウ病の人の妊娠は、ホルモン機能が正常な状態で
バセドウ病では、月経不順になることがありますが、排卵がなくなることはめったにありません。治療をして、ホルモン濃度が正常に保たれていれば、病気が不妊の原因になることはありません。
ただし、妊娠は、甲状腺機能が正常になってからにしたほうがよいでしょう。
※なお、手術や放射線ヨウ素(アイソトープ)治療を受けた人は、治療後1年間は、甲状腺機能が変動するので、できれば妊娠を避けるようにします。
妊娠してからバセドウ病が見つかった場合
それまで病気一つしなかった人が、妊娠中にバセドウ病が発見されることがあります。
甲状腺ホルモンが過剰な状態は、母体にも胎児にもよくないので、すぐに抗甲状腺薬で治療を始めれば、出産できます。
薬剤の胎児への影響
甲状腺の病気の人は、妊娠中も治療をつづけますので、飲んでいる薬が胎児にどのような影響をあたえるか、特に催奇(さいき)性(奇形を誘発)については気にかかります。
薬剤の胎児に対する影響や催奇性に関しては、妊娠のどの時期に薬剤を服用したかが重要です。
受精前から妊娠3週まで
受精後2週間以内に薬剤による影響を受けた場合は、着床しなかったり、流産して消失するか、あるいは完全に修復して健児を出産します。
妊娠4週~7週まで
この時期は、中枢神経、心臓、消火器、四肢(しし)などの重要臓器の器官形成期で、薬剤などによる催奇性が疑われる胎児にとって、もっとも敏感な時期です。
妊娠8週~15週まで
この時期は、胎児の器官形成は終了し、薬剤による胎児の影響はかなり低下します。
妊娠16週~分娩まで
この期間は、薬剤による奇形発生はありません。
バセドウ病の治療薬・抗甲状腺薬については、妊娠を希望されている方は、まずPTU(プロピルチオウラシル)を選択するほうが無難とされています。
ただし、MMI(チアマゾール)のほうが効果は確かなところがあります。そのため、日本甲状腺学会の治療ガイドラインでは、MMIを服用中に妊娠がわかっても8週目を過ぎていれば、PTUにかえなくてもよいとしています。
バセドウ病の人は、妊娠で症状が軽くなることも
妊娠10週ごろをピークに胎盤から分泌されるヒト絨毛(じゅうもう)性ゴナドトロピン(hCG)は、甲状腺を刺激して、甲状腺ホルモンをわずかに上昇させる働きがあります。このため、妊娠初期に見られる甲状腺機能亢進症は、このhCGによる妊娠性一過性甲状腺機能亢進症(一般妊婦の2~3%発症)か、バセドウ病の発病か、その鑑別が必要となります。
バセドウ病の人も、妊娠すると、26%の人は最初の3カ月(第1期)は、このhCGのためにバセドウ病が少し悪化します。しかし、4~5カ月(第2期)くらいになると、だんだん甲状腺機能が安定してきて、この第2期から最後の3カ月(第3期)にかけてはフリーT4の正常基準値は確実に減少します。これは、妊娠にともなう免疫状態の変化によるものとされています。
抗甲状腺薬は、胎盤から胎児へと移行するので、胎児の甲状腺が機能し始める妊娠20週以降は、胎児の甲状腺機能低下を避けるために、妊娠合併症がない場合には、フリーT4値を非妊娠時の正常上限付近に維持するように薬の量を調節します。そのため、薬の量が減り、場合によっては薬を中止できる可能性があります。ただし、これで病気が治ったわけではなく、ほとんどの人は出産後、また悪くなる場合が多くなります。
出産後も薬の治療はつづける
バセドウ病の状態にもよりますが、出産後も抗甲状腺薬の服用はつづける必要があります。産後には、病気が再発したり悪化することがあるからです。
薬を飲んでいても授乳は可能
出産後は、母乳で育てたい場合、抗甲状腺薬のPTUは1日300mg以下、MMIは1日10mg以下であれば、完全母乳でだいじょうぶとされています。
出産後の甲状腺機能異常
出産後は、橋本病やバセドウ病が一時的に悪化することがあります。また、無痛性甲状腺炎が起こることもあり、全産後女性の20人に1人が、出産後、何らかの甲状腺機能異常が起こるといわれています。
この状態を、産後の肥立ちが悪いとか、育児ノイローゼとかんちがいしている人も多く、種々の症状がある人は、甲状腺機能の検査をすることをおすすめします。
甲状腺機能異常が起こる理由としては、もともと甲状腺の異常があった場合、妊娠・出産というストレスによって母体の免疫系が乱れ、甲状腺の細胞が破壊されて、甲状腺ホルモンが漏れ出てしまうためです。その結果、甲状腺機能が約3カ月間一時的に上昇しますが、その後、甲状腺機能が低下して、多くは自然に機能が改善します。
さらに遅れて、出産後5~8カ月に発生する甲状腺ホルモン上昇は、バセドウ病の可能性が高く、抗甲状腺薬が必要となります。甲状腺自己抗体陽性が明らかな妊婦は、産後2~3カ月と6カ月に、甲状腺機能検査をしたほうがよいでしょう。産後も、医師に継続して経過を見てもらうことが大切です。
母親の自己抗体がもたらす新生児バセドウ病
バセドウ病の母親から生まれた赤ちゃんには、まれにですが、新生児バセドウ病が起こることがあります。
バセドウ病の自己抗体(TRAb)は、母体から胎盤を通って胎児の甲状腺を刺激するので、妊娠中に母親が抗甲状腺薬を服用していれば、胎内にいる赤ちゃんも自然に治療されています。ただし、生まれたあとは、母体からの薬の供給がなくなるため、赤ちゃんは一時的に甲状腺ホルモンの濃度が高くなります。これが新生児バセドウ病です。
3カ月で抗体は消え、治る
新生児バセドウ病は、事前に母親のTRAbが高い場合は予測ができます。さらに、生後すぐに赤ちゃんの甲状腺ホルモン(フリーT4、フリーT3)や、甲状腺刺激ホルモン(TSH)を測定すれば、甲状腺機能亢進があるかどうかがわかります。
症状が強い場合は、短期間、抗甲状腺薬による治療をすることもありますが、母親からの免疫である自己抗体は3カ月以内にはなくなりますので、自然に治っていき、症状は一時的なものです。
新生児バセドウ病は、遺伝性のものではなく、将来に影響もなく、あまり心配はありません。
ただし、以上のように、甲状腺機能異常は、妊娠前から出産後数カ月間、母児ともに長期にわたり影響をあたえますので、甲状腺専門医、新生児科医、小児科医とが上手に連携して診療にあたることが重要です。